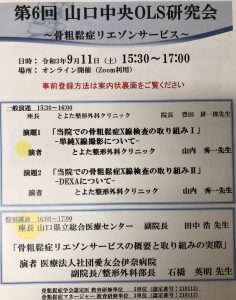8/29 10時から慢性疼痛マネジメントセミナーウェブ講習会に参加しました。キーワードは患者さんにセルフマネジメントを気づかせる、でした。
最初に日本慢性疾患セルフマネジメント協会の岡谷先生の患者さんがセルフマネジメントするために必要な医療者の対応についての講演を拝聴しました。
慢性疾患セルフマネジメントプログラムというスタンフォード大学で開発されたプログラムで病気の種類を問わず毎週一回2時間半計6回学ぶプログラムです。2人の進行役をリーダーとしてうち1人は慢性疾患を持っており前もって研修を受けるそうです。
症状・治療、生活、感情の3つの課題で困っていることに自己管理で対処する技術を伝えることが目的だそうです。良い睡眠を取る、呼吸法、筋のリラクゼーションを学び、コミュニケーションの取り方、問題解決法、意思決定の仕方、アクションプランなどを学び実行するとのことでした。アクションプランでは何をどれだけ、いつ、1週間に何回、自信レベルを書き出していくそうですので自己効力感を高め、グループで行うことで他者の成功体験を聞くこと、問題解決の支援ができることも持続効果も期待できるそうです。2005年から行われ山口県でも周南市で今年3月に開催されていたことを初めて知りました。最近はオンラインワークショップに取り組んでいるそうです。
次いで八千代病院痛みセンターの平林先生の講演「痛みに悩む患者の精神療法〜痛みがあっても自分らしい人生を送る秘訣とは?〜」を拝聴しました。共感とは相手の立場になって想像することで相手の気持ちや経験を共有することで、患者さんへの関心を持ち、これまでの努力を労り、回復を共に探ることですが中々難しいです。先生は森田療法の専門家として高名で、性格(パーソナリティ)を把握して治療されるそうで、痛みが主観的ですが回復も主観的で個別のものとのことで患者さんの持つ健康な側面を実生活で生かしてこそ真の痛みからの解決があるとのことで参考になりました。